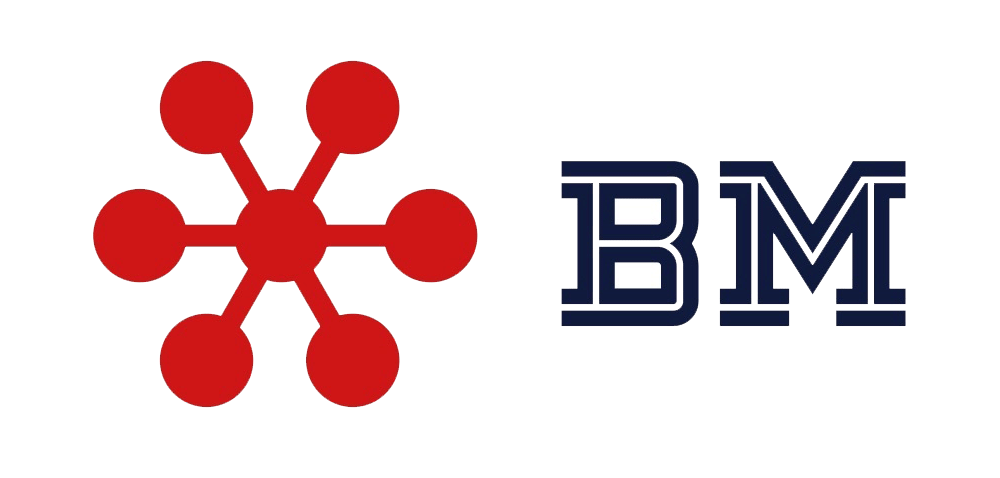もくじ
災害と二次火災に備えるために
昨今、世界各地で異常気象が報じられ、日本でも観測史上初となる気温上昇、火山噴火の懸念、地殻変動による地震の多発など、災害リスクが高まっています。
建物防災を仕事としている私から、日々の防災に役立つ情報をできるだけ簡潔にお伝えいたします。今回は「二次火災」と、身近な消防設備である【消火器】の正しい使い方についてまとめました。
二次火災とは
二次火災とは、大規模災害(地震などの一次災害)が原因で派生的に発生する火災のことを指します。
主な原因
• 電気配線のショート
地震による配線の損傷や接触不良で発火することがあります。
• 暖房器具の転倒
ストーブや電化製品が倒れ、可燃物に引火するケースです。
• 火やガスの不始末
地震によるガス漏れや火の散乱が火災につながります。
消火器の使い方【3ステップ】
🔥 覚え方は「ピン・ホース・レバー」
1. ピンを抜く
安全ピン(黄色や銀色)をしっかり引き抜きます。
2. ホースを火元に向ける
炎の先端ではなく「根元」に向けるのがポイントです。
3. レバーを握る
レバーを力強く握り、ほうきで掃くように左右に噴射します。

初期消火の3つの注意点
• 逃げ道を確保してから使用
背後に出口を確保し、退路をふさがないようにしましょう。
• 炎が天井に届いたら危険信号
その場合は消火器では手に負えません。すぐに避難して119番へ。
• 近づきすぎない
消火器の噴射距離は2〜5m。距離を保って使用すれば安全です。
まとめ
災害は誰にでも起こり得ます。
二次的な火災を完全に防ぐことは難しいですが、 「ピン・ホース・レバー」 という3ステップを覚えておくだけで、有事の際に冷静に対応できる可能性が高まります。
どうかこの内容を頭の片隅に置いて、日々の防災意識に役立てていただければ幸いです。
チームビーエムにご相談ください!
私たちチームビーエムは、法令点検のプロとしてだけでなく、「現場に根ざした防災支援」と「人材との連携による実行力のある仕組みづくり」を支援しています。
安全を“紙の上の計画”で終わらせない。現場目線のリアルなサポートをご提供します。